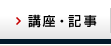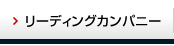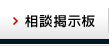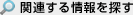第43回 退職者の住民税
これまでのコラムで退職者に対する社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)や雇用保険料の控除方法について紹介をしてきました。
今回は、住民税の概要と、退職者の住民税の手続きを中心に見てきたいと思います。
<住民税の概要>
住民税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。普通徴収は、サラリーマン以外の個人事業主や退職して次の就職先が決まっていない方などが、自分自身で住民税を納付することを言います。
一方、特別徴収は、会社が毎月の給与から天引きをして、本人に代わって各市区町村に支払うことをいいます。普通徴収でも特別徴収でも、年間の住民税総額は一緒ですが、特別徴収は毎月給与から控除されるのに対し、普通徴収の場合は年4回に分けて支払う仕組みになっています。そのため、普通徴収の方が、特別徴収に比べて納税の負担感が多くなると言われています。
会社で行う手続きは特別徴収になりますので、今回は「特別徴収」について説明します。
<特別徴収の仕組み>
住民税の特別徴収は、毎年6月から翌年5月にかけて、前年の所得によって計算された住民税の金額を毎月の給与から天引きします。
特別徴収の対象者は、毎年4月~5月の間に決定通知書が各市区町村から送付されてきます。この決定通知書に基づいて、各月の金額を毎月の給与から控除します。決定通知書にすでに退職した従業員が記載されていることがありますが、その場合は後で出てくる「給与所得者異動届出書」により、すでに退職していることを該当する市区町村へ報告します。
通常は、住民税の年額が12等分され、端数は最初の6月分に加算されます。したがって、住民税額は6月分が少し多くなり、7月分以降は定額となります。ただし、何らかの事情により、年度の途中で金額が変更になることがあります。給与計算の担当者は、各市区町村から決定通知書が届いたら、対象者と金額が変更になる月をかならず確認しましょう。
<退職者の住民税>
住民税を特別徴収している従業員が退職する場合には、退職日によって住民税の徴収方法が変わります。
1.6月1日から12月31日までに退職する場合
1)住民税の残額すべてをまとめて給与から控除することでその年度の納付を完了させる(一括徴収)か、2)普通徴収に切り替えて残りを個人で納付するかを、退職する従業員本人が選択することができます。
1)の一括徴収は、退職する従業員からの申し出により行います。そのため、特に申し出が無ければ、退職月分までを特別徴収し、残額は普通徴収に切り替えることになります。
なお、退職月の給与が少なくて、住民税を控除すると給与がマイナスになるような場合は、退職月の前月分までを特別徴収により控除し、退職月以降の住民税を普通徴収に切り替えても構いません。
2.1月1日から5月31日までに退社する場合
本人からの申し出がなくても、給与から一括徴収をすることが原則となります。ただし、一括徴収すると給与がマイナスになるような場合などは、退職月分までを給与で控除して、残りを普通徴収に切り替えることが可能です。
一括徴収が原則と言っても、従業員に無断で全額を控除すると、日々の生活に支障が出てしまうなどのトラブルの原因になることがあります。あらかじめ、退職者には一括徴収になることを伝えておいた方が良いでしょう。
<給与所得者異動届出書について>
特別徴収の対象になっている従業員が退職したときは、退職日の翌月10日までに、住民税の納付先である市区町村へ「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出します。提出先が現住所ではないことに注意してください。
この届出書で「一括徴収」をするのか、「普通徴収」に切り替えるのかを報告することになります。普通徴収に切り替える場合は、何月分までを特別徴収で控除したのかを良く確認して記入しましょう。
また、すでに転職先が決まっている社員の場合は、この届出書を市区町村ではなく転職先の会社に提出し、転職先で特別徴収を継続してもらうことになります。
なお、住民税は従業員が退職した場合だけでなく、休職や育児休業などで支払う給与がなく、特別徴収の継続が困難な場合も普通徴収に切り替えることができます。
以前は特別徴収を行っていない会社も多くあったようですが、近年では、特別徴収をすることができない特別な理由が無い限り、会社は特別徴収をすることが義務付けられています。
住民税額の徴収誤りや、給与所得者異動届出書の未提出などがあると、訂正するための余計な事務作業が発生するばかりだけではなく、まとまった金額の納付が必要になるなど従業員や退職者へ負担をかける結果になることもあります。
特に最近になって住民税の特別徴収を始めた会社は、あらためて住民税の手続き方法を確認しておいた方が良いでしょう。
 |
鈴与シンワート株式会社 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問 |
|---|---|
|
経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。 (有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。 |
|
専門家コラムナンバー
- 2026年に注目すべき中国経済の成長分野 (2025-09-25)
- EUのAI法にどう対応するか:企業が押さえるべきポイント (2025-09-10)
- グローバル企業が外部契約者を活用するべき5つの理由 (2025-09-04)
- グローバルM&Aにおける「孤立した従業員」問題の解決に向けて (2025-08-26)
- 第137回 退職者に対する賞与の支給 (2025-08-25)